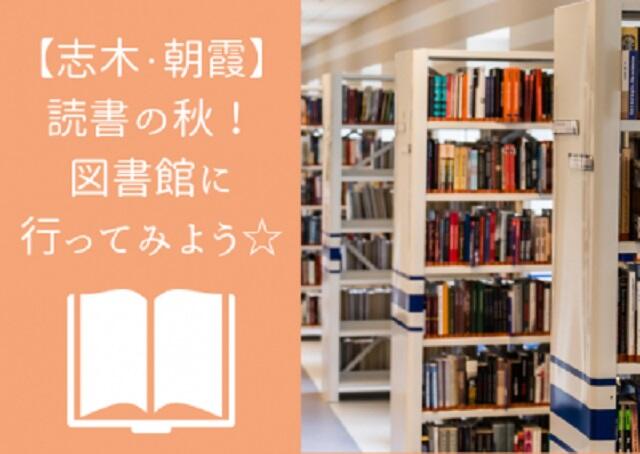知っ得!:
知っ得!:
子どものお小遣い・報酬制っておすすめ?
こんにちは!「志木と朝霞のママさんを応援!」ステキライフ編集部です♪
子どもの小遣いの与え方はどうしていますか?
「報酬制」「定額制」「都度制」など......。
どうやって渡すのか、迷うところですよね💦
それぞれにメリットとデメリットがあり、どの方法で与えるのか...
パパママの悩みの1つではないでしょうか❓
今回は、その中でも「報酬制」についてのメリットやデメリット。
気をつけるポイント、お手伝いの内容や
勉強やスポーツの成績によって与える方法の問題点について解説します!

子どもの報酬制、メリットやデメリット、気をつけるポイント
報酬制とは、お手伝いや学校、スポーツの成績などに応じてお小遣いを渡す方法です。
まずはメリットやデメリット、気をつけるポイントについて見ていきましょう。
メリット
報酬制のメリットには以下のことが挙げられます。
● 社会におけるお金の流れがわかる
働くとお金がもらえる、そのお金を使って生活する等
という社会におけるお金の流れを知ることができます。
● お金のありがたみが実感できる
労働の対価としてお金をもらうため、お金のありがたみがわかりやすいです。
親が働いたお金で生活していることに対する感謝の気持ちも育つかも?!
● 手伝いが習慣になりやすい
家事を手伝う習慣がつきやすく、将来の生活力が向上。
デメリット
報酬制のデメリットには、「奉仕の精神が育ちにくい」ことが挙げられます。
報酬制だとお金をもらわないと働かなくなることがあるかもしれません。
「家族や他人のために無償で何かをする」という奉仕の精神が育ちにくくなります。
また、何をするにしても、お金を要求するようになるかもしれません。
気をつけるポイント
報酬制を導入する際のポイント
● 「家の仕事を手伝うのは当たり前」であることを前もってしっかりと伝えておきましょう。
● 自分の家では労働に対する対価としてお小遣いをあげることも理解させておく必要があります。
また、自分のことに対してはお金をあげないことも大切。
自分の身の回りのことは自分がする!と教えましょう。
子どもができるお手伝いって?
家庭の状態や子どもによってできるようになる年齢は異なります。
自分の子どもができるお小遣いを選びましょう!
● 風呂掃除
比較的低学年からできますが、水を使うのが不安な場合は年齢が上がってからがおすすめ。
● ゴミ捨て
低学年のうちはゴミの分別だけでも。
● 洗濯物を干す、取り込む、たたむ
洗濯物をたたむことは低学年からできます。
年齢が上がるにつれて、取り込む、干すも取り入れるといいでしょう。
● トイレ掃除
トイレ掃除は教育的にもおすすめ。
とくに男の子は汚しがちです。
家族みんなが快適に使えるようにすることの大切さを学ぶことができます。
● 玄関掃除
低学年のうちは靴を揃えるだけでも。
年齢が上がってきたらホウキを使って掃除をするようにしましょう。
● 食器洗い
低学年のうちは洗った食器を拭くだけでもOKです。
● 配膳・食卓の準備
低学年のうちは、箸を揃えて家族のお茶碗を用意するだけでもいいでしょう。
年齢が上がるにつれて、食器によそう、配膳するなどを追加してみるのも◎
勉強やスポーツの成績と報酬を連動させる弊害とは
報酬制では、勉強やスポーツでよい成績を取るとお小遣いがもらえる、
報酬額がアップしたりする制度を採用する家庭もありますが、これには弊害があります。
● サッカーなどの集団競技で、上記のように報酬がもらえる場合
ついつい自分でゴールを決めようとスタンドプレーに走ったり、
チームメイトのミスが許せなくなったりすることがあります。
● よい成績を取ったらお小遣いがもらえる場合
お金をもらわないと勉強しなくなる、
お小遣いが必要ないことを勉強しない言い訳をする機会が増えるかもしれません
● スポーツや勉強が苦手な場合
お小遣いの報酬制度自体がストレスになってしまうこともあります。
まとめ:報酬制にする場合は工夫をしよう!
報酬制についてはいろいろな意見があります。
「ニンジンをぶら下げてお手伝いをさせたり勉強やスポーツをがんばらせたりするのはよくない」
という考えもあります。
しかし、デメリットを克服できると働くことの大切さを身をもって学ぶことができます。
採用する場合は、保護者がよく考えてあげましょう。
お手伝いを選ぶ際には、子どもの年齢や成長に合ったものを選択しましょう。
また、子どもがお手伝いをした時は、「ありがとう!助かるよ!」など。
感謝の気持ちを伝えることも忘れてはいけない大切なポイントです。
子どものお小遣いに報酬制を採用する場合、
お手伝いを通して働くことの大変さ、大切さを。
対価としてお金をもらうことのありがたさを子どもが素直に学べるようにしましょう。