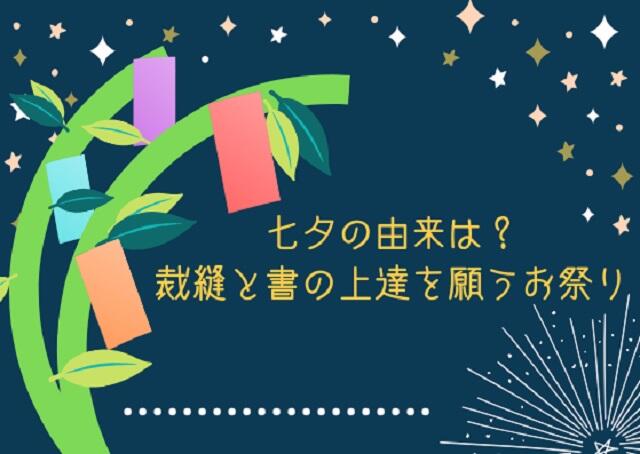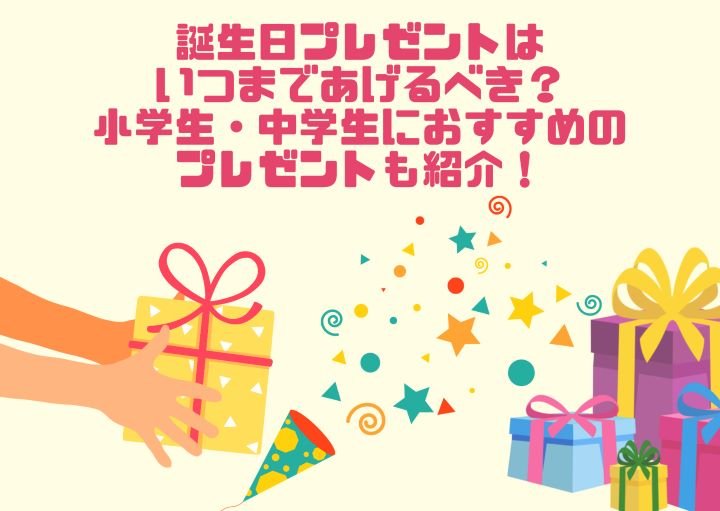七夕の由来を知ってる?
こんにちは!「志木と朝霞のママさんを応援!」ステキライフ編集部です💕
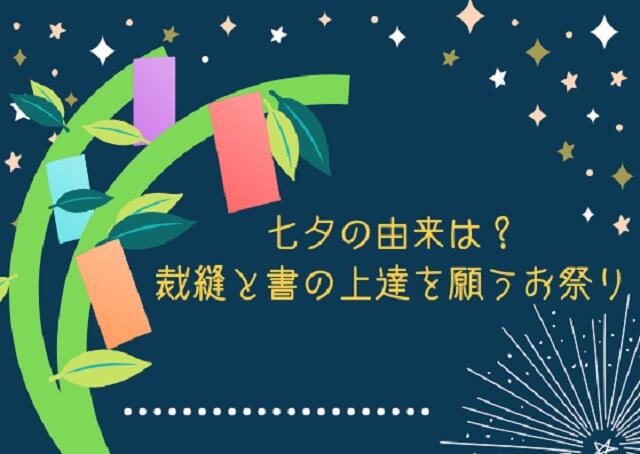
笹の葉さらさら~♪7月7日は七夕ですね☆
お家で短冊を飾って、七夕を楽しんでいるママさん・パパさんも多いことでしょう。
さて、七夕の由来について、ママさん・パパさんはご存知ですか?
おりひめとひこぼしの七夕伝説については知っているママさん・パパさんも多いと思います。
今回は、七夕の由来や、七夕のときにするとよいとされる願い事を紹介します♪
七夕の由来 中国から日本へ<七夕伝説>
中国の「乞巧奠(きこうでん)」
琴座のベガと呼ばれる織女(しゅくじょ)星は裁縫の仕事、鷲(わし)座のアルタイルと呼ばれる牽牛(けんぎゅう)星は農業の仕事をつかさどる星と考えられていました。
この二つの星は旧暦7月7日に天の川をはさんで最も光り輝いているように見えることから、
中国でこの日を一年一度のめぐりあいの日と考え、七夕ストーリーが生まれました。
このことから、女の子が織女星のように裁縫が上手になるようにお祈りをするようになりました。
これが「乞巧奠(きこうでん)」という中国の習わしです。
乞巧奠は、奈良時代ごろ、日本に伝わりました。
日本では、古くから7月7日の七夕(しちせき)の節句に合わせて、若い女性が機を織り、それを神棚に捧げることで、五穀豊穣を願う習わしがありました。
この機織りに使う道具を「棚機(たなばた)」といい、この読みが、現代にも伝わっているそうです。
平安時代では貴族の間で、江戸時代になると、その風習が庶民の間にも伝わっていきました。
庶民の間で、五行の色にちなんだ五色の短冊や吹き流しを飾って、願い事をするようになり、
これが現代の七夕として残っているのではないか、と伝えられています。
七夕は裁縫と書道の上達を祈る行事?
おりひめが裁縫を営んでいたことや、「棚機」が機織りに関する風習があることから。
古くから七夕は裁縫などの上達を願う行事としても、定着してきます。
中国の乞巧奠では、もともと裁縫だけでなく、書道や文学に関するお願い事もされていました。
江戸時代に庶民の間に七夕が定着したころ、書道の上達を祈るという要素が加わっていったとされています。
平安時代の宮中行事では、芸術を楽しむ行事が多く、裁縫だけでなく、書道や文学・詩歌などの芸事の上達を願う要素が出てきたのではないか、とも考えられています。
※諸説あります
まとめ:七夕でそうめんを食べるのはなぜ?
七夕の行事食と言えば、そうめんが知られています。
行事食としてそうめんが出されるようになったのは、平安時代の頃。
おりひめが機を織るときの糸や、天の川の流れに似ていることから、行事食として定着してきました。
※諸説あります。
色付きそうめんは、五行の色にちなんでいます。
お家でかわいいくアレンジして食べてみてはいかがでしょうか。
ぜひ、お家で七夕を楽しんでみてください。