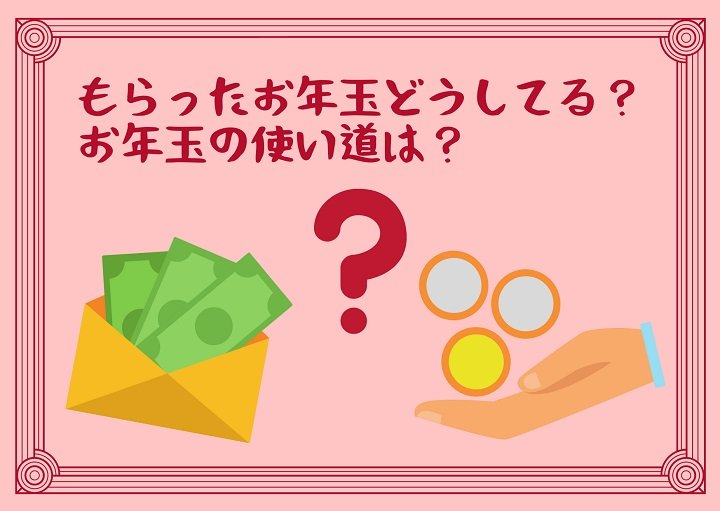 知っ得!:
知っ得!:
お年玉について考えてみよう
こんにちは!「志木と朝霞のママさんを応援!」ステキライフ編集部です♪
お正月にもらったお年玉。誰が管理し、どんな使い方をしていますか?
子どもが年に一度、高額なお金を手にするタイミングは、親も子もお金の価値や使い道にじっくり向き合う絶好の機会です!
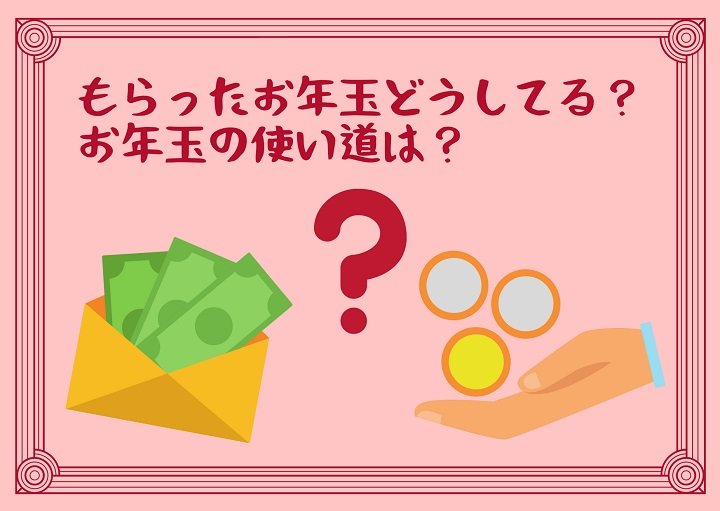
年代別の使い道は?
貯蓄好きと言われる日本人ですが、お年玉も「とりあえず貯金する」という声が多く聞かれます。
◇乳幼児(0歳〜2歳)
この年代はそもそもお年玉をまだもらっていないというご家庭も多いですよね。
もらった場合は、まだ子ども本人がお金を使ったり、使い道を考えたりといったことが難しいため、親が管理するケースが大半です。
◇未就学児(3歳〜6歳)
幼稚園・保育園の年少あたりから、お年玉をもらい始めるケースが増えてきます。
貯蓄以外では、おもちゃや絵本、お菓子など、少額のものを子ども自身が選んで購入するという意見が多いようです。クリスマスや誕生日に高額なプレゼントをして、お年玉は貯蓄と区別しているご家庭も☆
◇小学生
小学校にあがると、お年玉の相場も少し上がってきますね。ゲームソフトを欲しがったりと、欲しいものが高額な商品になってくるのもこの年代から...。
お年玉の一部を自分で自由に使えるお金として手元に残して、残りは貯金するというケースが多いようです。
◇中学生
この年代になると、友達と遊ぶための交際費にするという使い道が増えてきます。
また、このくらいの年齢になると全額を子ども本人が管理するというご家庭も増えてきます!
◇高校生以上
何歳までお年玉をもらうかは、高校生まで、成人するまで、大学卒業まで、など家庭によってさまざまですね。
高校生になると、子ども自身が自由に使っているという意見がほとんどになってきます。
アルバイトもできる年齢なので、自分で考えて自由に使うのも納得です!
誰がどのように管理すべき?
子どもに預けるべきなのか、親が管理すべきなのか、何歳からどうしたらよいのか悩みますよね。
お年玉は、親が子供名義の口座に貯金するなどの管理をして、子どもが大きくなるにつれて、自分で使い道を決める金額が高額になっていくというパターンが多いようです。
また、親世代が子どもだったころと違い、低金利の今、とりあえず貯金することが正しい管理の仕方とも言い切れません。
「欲しいものを買う」という現金の使い方を話し合うのと同時に、お金の増やし方についても教えて金銭教育をしていけるとなお良いですね!
最近では、子ども名義の銀行口座を開設するときに、同時に証券口座を作り、投資信託を選んで積み立てを始める方もいるそうです。
親が管理するというと「口座に入金し記帳する作業」というイメージが浮かびやすいですが、「投資を始めて親子で一緒に運用状況をチェックする」という管理の仕方もあります!
お金の使い方を学ぶ良い機会に!
お金の使い方を学ぶには、実際に自分で考えてお金を使って買い物をしてみる経験が大切です!
小さいうちは貯金がメインでも、大きくなるにつれて子ども自身に考えさせ、行動させる機会を増やしていくのも良いですね◎
そのときにポイントとなるのは、「親が口出しし過ぎず、子どもに主導権を握らせてあげること」です。
子ども自身が使い道を計画して、親はアドバイスをする程度にとどめれば、子どもの自主性が育まれます!
「大きな金額を無駄遣いしてしまうのでは?!」とつい口出ししたくなってしまいますが、最近では「あえて無駄遣いさせた方がよい」という教育論もあるのだとか。
お年玉を仮に無駄遣いして失敗したとしても、その経験がお金の大切さを学ぶことにつながっていくという発想です。全額ではなくても、金額を決めて、その金額の範囲内で子どもが自由にしてよいと決めるのもいいですね。






