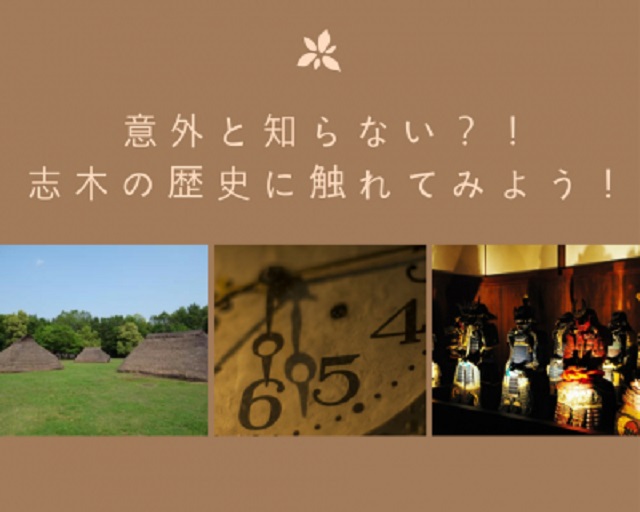
新しい市だけど歴史は奈良時代から!
こんにちは!「志木のママさんを応援!」ステキライフ編集部です♪
さて、2020年には市制50周年を迎える志木市。市としての歴史は短いのですが、志木には歴史を感じるものが多く残されています。例えば、市役所の目の前には旧村山快哉堂、また市役所の付近にはいろは樋の大桝や引又観音堂、朝日屋原薬局、旧西川潜り門はおなじみですよね。
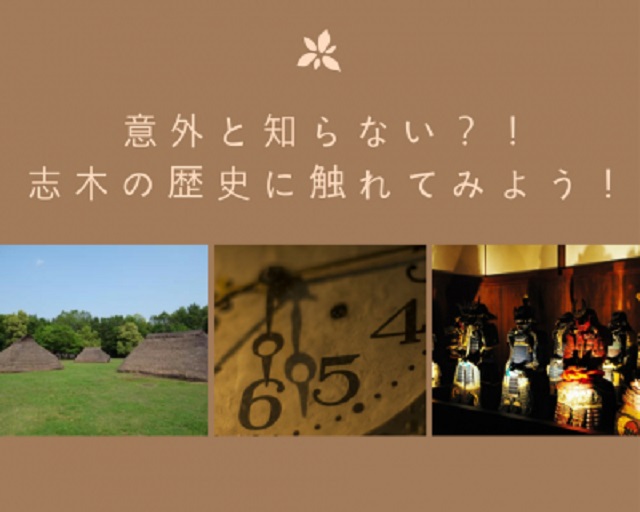
志木には一体、どのような歴史があるのでしょうか?また、地名にはどのような由来があるのでしょうか?今回、ステキライフ編集部は、志木の歴史や地名の由来を調べてきました♪
驚き!「新座」の由来は「新羅」から!?
志木市は1955年に、現在の志木地区にあたる志木町と宗岡地区にあたる宗岡村が合併し、1958年に当時の朝霞町の一部が合併して今の形になりました。志木地区は、北足立郡に変わる1896年までは新座郡、宗岡地区は入間郡と、郡も違ったのですよ!
そんな新座郡の名前の由来は、新羅郡から。天平時代(758年)に、この地に朝廷が新羅(現在の朝鮮半島の東側)からやって来た僧侶ら74人を、武蔵国で当時未開発だった場所に移住させたのが始まりと言われています。
平安時代以降、栄えた歴史ある地区・館
平安時代末期には、現在の館地区に、田面長者藤原長勝という伝説の豪族が居宅を構え、地域を治めていたと言われます。柳瀬川が東北にあるので、防衛上有利だったのです。その後、数回の地名変更を経て10世紀には舘村になったようです。
舘之郷にあった幻の城と幻の村
江戸時代初期以降の文献や石仏からは、舘之郷という地名があったことがわかっています。
舘之郷には、幻となってしまった城や村があった記録が残されています。その代表格は志木第三小学校付近に、1590年まであったとされる柏ノ城です。豊臣秀吉が小田原を攻略したときに滅ぼされてしまいますが、戦国時代初期から大石氏がこの城に住んでいたと言われています。
柏ノ城無き後は、開発され中野村として独立しますが、18世紀最後に名主が死亡すると衰退し、舘本村に吸収されてしまったようです。また、舘之郷には、大塚村という村もあったと言われています。中世の文献には「大塚」という地名も出てきますが、1692年長勝院の版鐘に記銘されたのを最後に、その名は語られなくなりました。
250年で独立した村より栄えていた引又村
一方、1576年に舘本村の住民が開発し住み始めた引又地区(現在の新河岸川・柳瀬川の合流地点付近)は、江戸時代以降、引又村として独立し、栄えていきます。野火止用水のおかげで農業生産力が高かったのと、舟運によって栄えたのです。
上の水車跡、引又河岸場跡、いろは樋の大桝は江戸時代から明治時代に造られたものです。また、敷島神社は、引又村の人々が進行していた3つの神社を合祀したもので、明治末期の1908年に建てられたものです。
引又村と舘本村は1874年に合併しますが、舘本村から独立した引又村が、この時期には舘本村よりも栄えていたことからどちらの地名を残すかで揉めます。そこで、かつてこの近くに「志木郷」という場所があったことから「志木宿」に落ち着きます。
明治時代に統合!宗岡地区
一方、入間郡に属していた宗岡地区ですが、室町時代中頃の文献に「宗岡」という地名が出てきます。その名前の由来は様々あるのですが、地名説が有力です。ただし、その地名説も複数あり、どれが正解かはわかっていません。
宗岡地区は、江戸時代には上中下の3つの村に分かれていました。その後、明治時代になってから1つの村にまとまっていきます。
郷土資料館では歴史を学ぶ講座も
志木の歴史は中宗岡3丁目にある郷土資料館でもくわしく学ぶことができます♪市民文化財講座、市民史跡めぐりなども開催されているようですよ。講座などは、毎月配られる「広報しき」をご確認ください♡
郷土資料館は志木駅東口から宗岡循環や浦和駅西口、西浦和車庫行きのバスに乗り、宗岡小学校で下車、歩いて1分です♪歴史を知ることで、町がもっともっと身近に感じられるかもしれませんよ♨
歴史を知ることによって、より地域愛が深くなりそうですね。『昔はこんなことがあったんだよ~。名前の由来はね…』なんて、お子さんに話してあげられると歴史に興味を持ってくれるかも。






