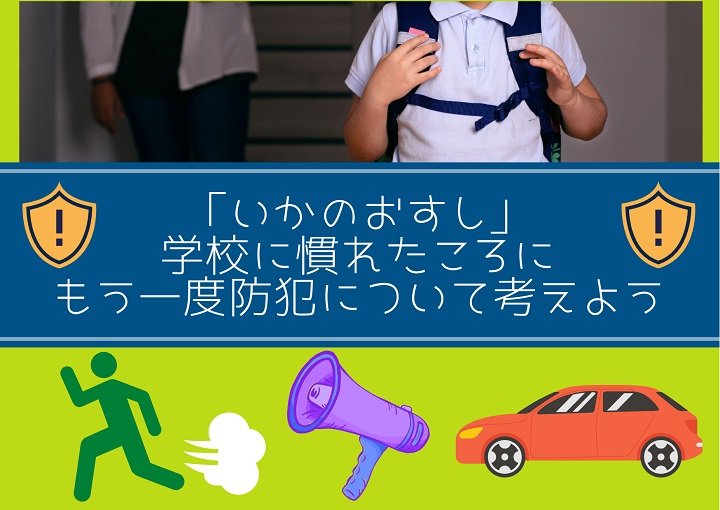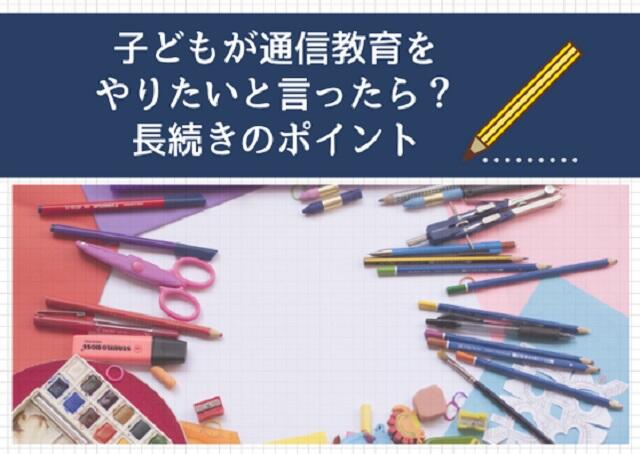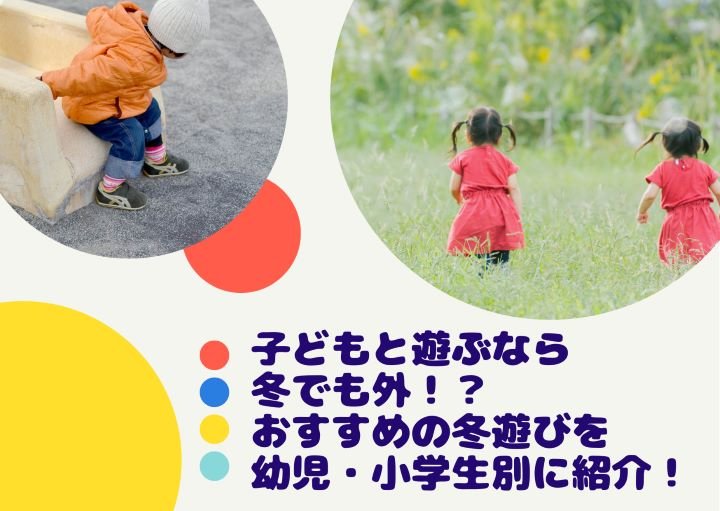何かが起こる前の対策が重要!
こんにちは!「志木と朝霞のママさんを応援!」ステキライフ編集部です♪
子どもが小学校に入ると登下校時をはじめ行動範囲がぐっと広くなり、一人で行動する場合も出てきます。
はじめは緊張して行動していた子どもも、学校に慣れてくるにつれてだんだん警戒心も薄くなりがち💦
そこで子どもにしっかりと教えたいのが「いかのおすし」!
この記事では、「いかのおすし」をはじめとする子どもの防犯対策について紹介します。
「いかのおすしって何?」と思う人。
「知っているよ」という人。
改めて子どもの防犯対策について考えることをおすすめします✨
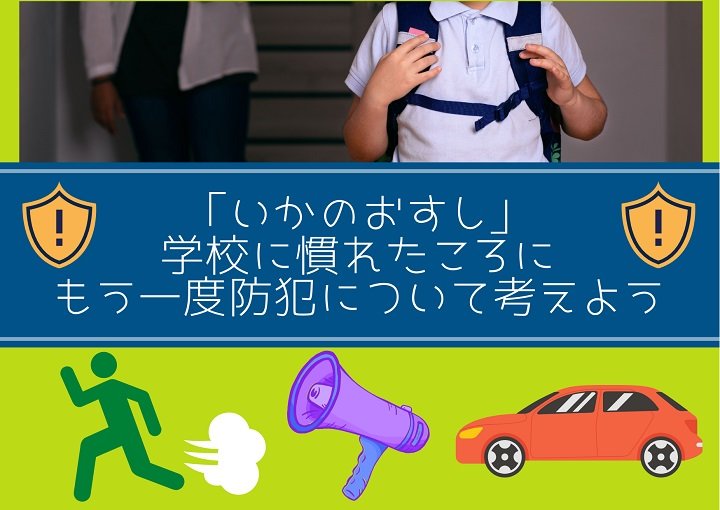
いかのおすしって?
「いかのおすし」とは、子どもが不審者に出会ってしまった時の対応策。
とっさの時に思い出しやすいように考えられました。
子どもの好きな「おすし」と「いか」に語呂合わせして考えられた言葉です。
● いか=「いかない」
【いか】は、知らない人について「いかない」こと。
知っている人でも「家の人に聞いてから」と言うように教えましょう。
自分以外の家の人がいない場合は
「○ちゃんのお母さん以外の人にはついていかない」
「ママかパパが帰宅してから」など。
日頃からよく知っていて信頼できる人以外に人にはついていかないように言い聞かせるといいでしょう。
● の=「のらない」
【の】は、知らない人の車には「のらない」こと。
車に近づいてしまうと力ずくで押し込められる可能性もあるため、近づかないようにします。
● お=「大声を出す」
【お】は、知らない人に連れていかれそうになった時に。
危ない、怖いと思ったりしたら「大声(おおごえ)を出す」こと。
声が出ないこともあるので、防犯ブザーをもたせるのがおすすめです。
● す=「すぐ逃げる」
【す】は、何かあったら「すぐに逃げる」こと。
足がすくんでしまうこともあるので、防犯ブザーは必須です。
● し=「知らせる」
【し】は、危険を感じることがあったら、必ず親に「知らせる」こと。
叱られるかも・・・と思って言い出せないことも考えらえます。
絶対に教えるように日頃から話しておきましょう。
危険な場所ってどんな場所?
犯罪が起こりやすい場所とは、「誰もが入りやすく、誰からも見えにくい」場所。
【例】
● 駐車場
● 公衆トイレ
● 周りが建物の道
● 放置されている空き家
● 倉庫タイプのごみ置き場...などがあります。
【子どもの行動範囲にこのような場所がある場合】
● 近づかないこと、
● やむを得ない場合は一人では近づかないこと、
● 周囲をよく確認すること...など
徹底して教えるようにしましょう。
どんな危険なのか具体的に教えておこう
いくら教えても子どもはどんなことが「危なさそう」なのかわからないこともあります。
知らない人がどんな声かけをしてくるのかを具体的に教えましょう。
【例】
● お菓子を買ってあげる
● 新しいゲームを一緒にしよう
● 向こうの公園の方が楽しいから一緒に行かない?
● 道がわからないから車に乗って教えてくれない?
● お母さんが病気になったので迎えに来た
● 雨が降っているから送っていくよ
子どもは咄嗟に返事をするのが難しいこともあります。
「親切を断ったら怒るかもしれない、失礼かもしれない」などと考えてしまう子どももいるのです。
一見親切のような声かけを断る際には、
「お母さんを呼んできます」
「お母さんに聞いてきます」など
母親がしっかり管理していることがわかるような断り方をさせましょう。
お母さんが病気になった事故にあったなどの声かけには「学校に戻るように言われています」と答えます。
また、正義感が強くなる小学生には「子どもに助けを求める大人はいない」と教えておくことも大切です。
対応策も具体的に
危ないときはどのように対応したらいいかも、日頃から具体的に指導します。
【例】
● 本当に困っているように見えたら「大人を呼んできます」と言ってすぐに学校か交番へ。
自宅の大人のうち場所が近い方に知らせる
● 人がいない場所には絶対に近づかない
● 一人で広場や公園で遊ばない
● 一人で道を歩かない、もし歩く時は人がたくさんいる道を歩く
● 逃げ込める場所は、学校、交番、子ども110番のステッカーが貼ってある家、コンビニ・スーパーなど
公園のトイレは要注意
トイレは生理現象なので、行かないようにと指導してもどうしても必要な場合もあります。
● 家と学校以外のトイレには一人では絶対に行かない
● どうしても公衆トイレに入らないと間に合わない時は、
友達と中を確認してから一人ずつ入り、お互いに大きな声で声をかけあう
● 多目的トイレの緊急ライトが光っていても、絶対に自分で助けようとせずに大人を呼ぶか電話をする
など、具体的に指導しておくことが重要です。
例外は作らないようにしよう
低学年の子どもの場合、「こんな場合は○○してもいい」などと例外を作ると混乱します。
子どもが
「もし本当に困っている人だったら悪いかなあ」
「本当にお母さんの友達で親切で声をかけてくれたら悪いことをする」などと不安に思うことも。
「間違っていたら後でママがきちんと謝ってくるから迷わずに逃げなさい」と指導しましょう。
今の時代、防犯意識が高いがための失礼で怒る大人はいないと考えていいと伝えましょう。
どうしても断れない大人しい子どもの場合は「お母さんに絶対にだめと言われているから」。
と母親のせいにさせるのも有効です。
まとめ:自分の安全を守る判断がつく子どもに!
子どもはどんどん成長し、親から離れて一人で判断したり行動したりするようになります。
「いかのおすし」を徹底し、自分の身を守る判断がつく子どもになるように導きましょう。
通学路や子どもがよく行く場所を子どもと一緒に歩いてみるのもおすすめです。
危険を感じたら逃げ込める場所を確認したり、防犯ブザーの使い方を練習したりしておくと安心です。
今はSOSを伝えられるGPSもあるようです。大人しい子どもの場合は持たせてみても良いかもしれません。