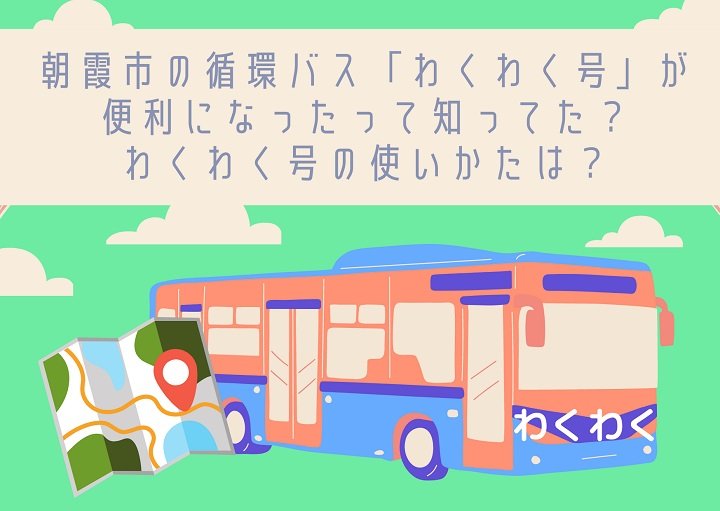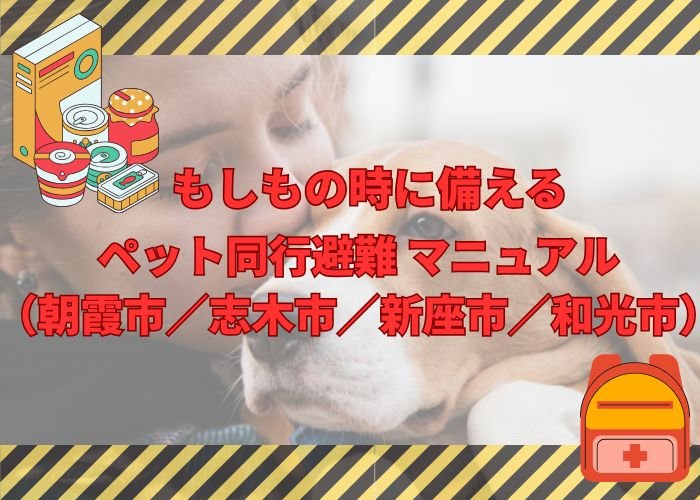
天災はいきなり起こるものです。
やはり、一家に一つは防災用具がなくてはいけないかもしれません。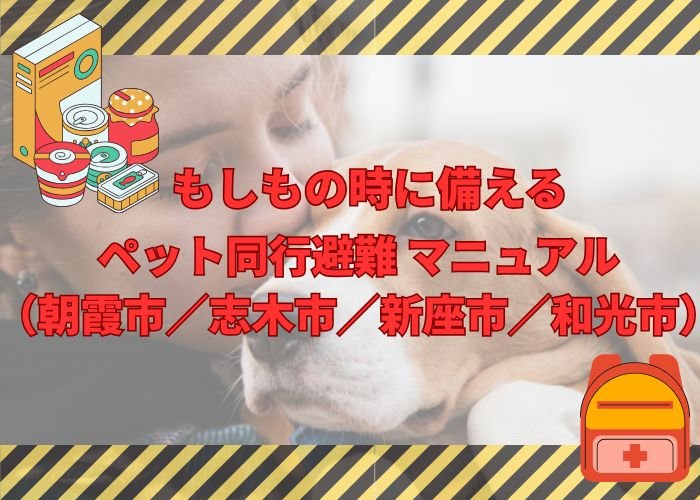
こんにちは!ステキライフ編集部です♪
もし、自分の住んでいる地域で地震や津波などの被害があったら...。
もし、家族がばらばらになったら。
考えると怖いことばかりですよね。
また、ペットを飼ってらっしゃる方も考えることがたくさんあるのではないでしょうか。
避難所にいっしょにいけるのか。
食べ物はどうしたらいいのか。 等
そこで、今回は災害時にむけたペット防災について紹介します!
朝霞市/志木市/新座市/和光市 の4市をピックアップ!参考にしてみてください。
ペット防災対策・お家でできること
災害時にはご家族やペットの安全確保が最優先事項です。
しかし、いざ自分が災害にあった時は動揺してしまうもの。
いろいろなことがおこり、パニックになってしまうかもしれません💦
普段からしっかりと、備えておくようにしましょう。
では、どんなものをそろえた方がよいのか、どれくらいの量が必要なのか。
しっかりと対策していきましょう。
【基本の持ち物】
● 十分な水や食料の他 ※ 5日~7日分程
● 常備薬等も用意
● 避難所や避難ルートを確認しておく等、
また、基本の持ち物に加え、ペットにきちんとしつけをしておくことが大切です。
● 日頃からキャリーバックやケージに入れることなどに慣れさせておく
● 吠えたりしないように対策を考えておく
● 予防接種をしておく(※狂犬病、寄生虫ワクチンなど)
● 首輪や名札・鑑札・狂犬病予防注射済票などをつけておく
持ち物をチェックしたら準備してみましょう。
家族でペットといっしょにどう過ごすのかを想定して計画してみてください。
また、各自治体のルールもあります。
ルールをチェックし、しっかりと日頃から対策しておくことが重要です。
各自治体別のペット防災
各自治体のペット防災対策を紹介します。
【朝霞市】
災害時の避難は、ペットと一緒に避難所に避難すること(=同行避難)が基本です。
ただし、市では避難所でのペットの受け入れについて次を推進しています。
● 原則、避難所でのペットスペースは屋外。※ 雨天時のために屋内スペースを用意します。
● 屋内スペースで受け入れ可能なペットは、
飼育ケージ、キャリー、カゴなどに入っている小型のペットです。
● 避難所には、ペット用の食料、備品等の備蓄はありません。
ペット用の食料、備品等は各自で用意してください。
「大型のペットの場合」
ペットが慣れている親戚や、知人、動物病院や民間団体など...
緊急時に預けられるか事前に確認をお願いしています。
大型犬は屋内のスペースて過ごすことは困難です。
慣れている人が少なく、なにかあった場合の責任が取れません。
朝霞市では、ペットの受け入れ可能な避難所をリスト化しています。
日頃からチェックしておきましょう。→ 朝霞市指定避難場所一覧
詳しいことは朝霞市のホームページで確認しましょう。→ 朝霞市ペット防災
【志木市】
災害時の避難は、ペットと一緒に避難所に避難すること(=同行避難)が基本です。
これは朝霞市でも同様です。
● 災害時に市内の小学校及び中学校を避難所として開設した場合
ペットの同行避難が可能です。
● 敷地内の屋外にペット専用スペースを設けます。そこへ連れていくことができます。
※屋内は禁止です。
また、ペットの備品は用意がありません。日頃から揃えておくようにしましょう。
志木市のホームページでは、ペットに必要な備品を公開しています。
志木市ペット防災
【新座市】
新座市の場合もペットといっしょの同行避難を推奨しています。
また、ホームページ上で明確なルールを掲載しています。一度確認してみましょう。
避難所でのルール
(1) 原則として、使用可能な外倉庫または屋外飼育となります。
※ ただし、盲導犬、聴導犬、介助犬等の補助犬は除きます。
(2) ペット避難スペースでは、ケージ等を使用し、ペット毎の空間を確保します。
避難の際は、ケージ等を忘れず!
(3) 避難所での飼育は、飼い主の方が全責任を負って行っていただきます。
(4) 避難所等には、ペット用品(餌等)の備蓄はありません。各自で用意が必要です。
⑸ 風水害時は、市民総合体育館をペット避難スペースとして開放します。
屋外での飼育が困難なため。
【和光市】
和光市も同行避難を推奨しています。
基本的なしつけはもちろん、防災に関してしっかりと備品を準備することが大切です。
● 日頃からキャリーバックやケージに入れることなどに慣れさせておく
● 吠えたりしないように対策を考えておく
● 予防接種をしておく(※狂犬病、寄生虫ワクチンなど)
● 首輪や名札・鑑札・狂犬病予防注射済票などをつけておく...等
上記の4つはどの自治体でも共通していわれています。
目を通しておきましょう。
災害はどこでも起こりうるものです。準備しておくことに越したことはありません。
少しづつでも防災に備えておきましょう。
防災ブックを活用しましょう!
埼玉県では、一般の飼い主さんへ防災ブックの活用を進めています。
避難所では動物が苦手な方やアレルギーを持っている方等へ特別な配慮が求められます。
また、ペットにとっても大きなストレスとなる可能性がある災害。
ペットの行動も考えた十分な準備をすることが重要です。
ペット同行避難ガイドライン、ペット動物のための防災手帳を活用してみましょう。
避難所等においては、自治体の指示に従いましょう。
ルールを遵守し、他の避難者に迷惑をかけてしまうことがないようにしましょう。
まとめ
ペットの防災について紹介しました。
どの自治体でも共通していることは、日頃から準備しておく、ということです。
特にペットの場合、備品は各自で用意することがほとんど。
また、同行避難とはいっても、ペットは屋外で過ごすことが求められます。
災害時の場合、多くの方々といっしょに過ごすことになります。
そのため、ペットにとってもかなりの負担があるでしょう。
飼い主としてできることは、可能な限り準備をしてあげること。
しつけを含め、慣れさせることではないでしょうか。
困難なことにはみんなで立ち向かうもの!
災害はいつどこで起こりうるかわかりません。
動揺を少なくするように、しっかりと準備しておくことが大切です。
あわせてこちらの記事も参考にしてみてください
【志木・朝霞版】今日から始める親子防災!ハザードマップ活用方法