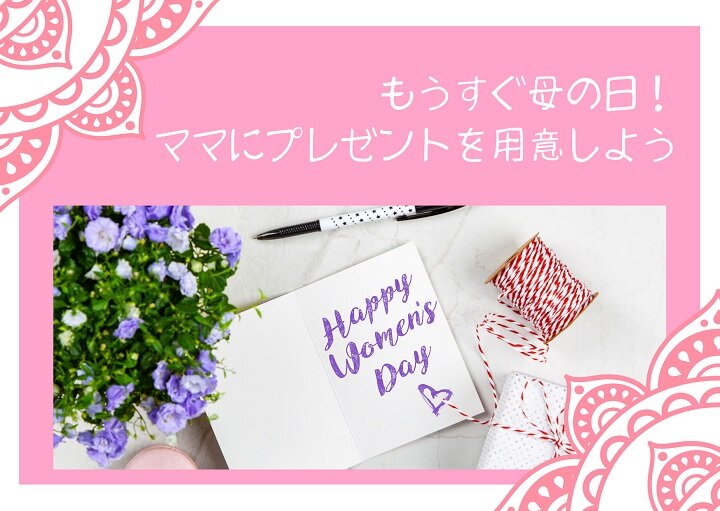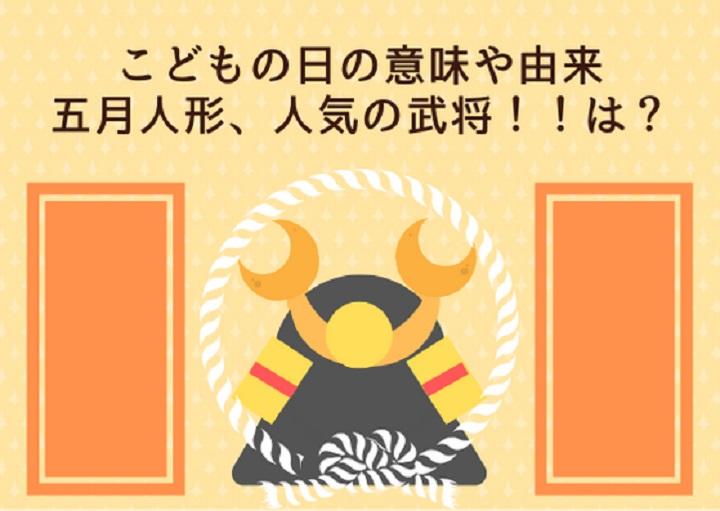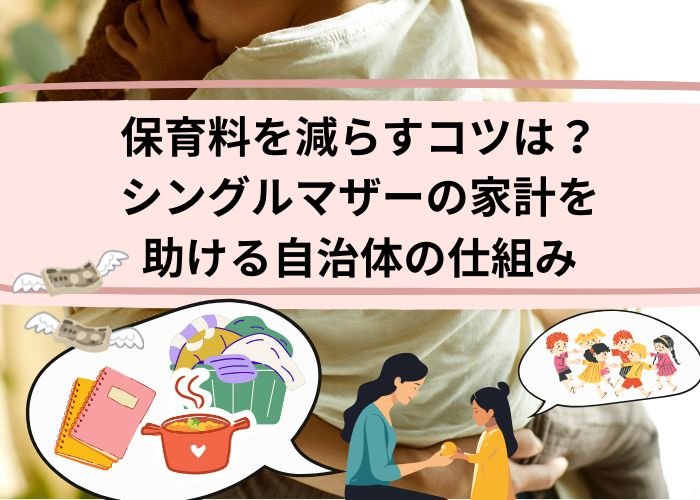
シングルマザーになったら、今後の生活のための資金について考えなくてはいけません。
結婚時に専業主婦だった方は自身で働く必要があります💦
金銭面での不安はとても大きなものになるでしょう。
ステキライフ編集部です!💕
特に子どもの養育費や学費などを、子どもが自立するまで用意しなくてはならず、悩むことも多いでしょう。資金に不安があるシングルマザーを支援してくれるのが、国や自治体による助成金です。
今回は、シングルマザーを対象とした助成金の種類、申請時の注意点などについて。
詳しく解説していきます!
保育料を減らすコツは?
シングルマザーが保育料を減らすためには、国や自治体の助成金、経済的な優遇制度を利用するのがいいでしょう。
保育料の軽減措置として
- 認可保育園や認定こども園などの利用料が軽減される「幼児教育・保育の無償化」制度の利用
- 兄弟の年齢差や同時に通う施設の数に関わらず第2子以降の保育料が軽減される
- 減税・減額制度を利用する(国民年金や国民健康保険の減免制度や、交通費の減額)
医療費助成制度を利用する...等
がありますが、それだけでは心配なことも多いです。
自治体や国の経済制度を利用してより資金を考えていきましょう。
シングルマザーのための助成金・手当!
国や自治体には、シングルマザーを対象とした助成金があります。まずは把握しましょう。
シングルマザーを対象とした助成金の種類をしっかりと把握し、生活に活かすことが大切です。
シングルマザーが受給できる可能性のある助成金・手当は次の通りです。
- 児童手当
- 児童扶養手当
- 児童育成手当
- 特別児童扶養手当
中には自治体独自の助成制度をもっているところもあります。
お住まいの地域に必ず確認しにいきましょう。
では、くわしくみていきます!
児童手当
中学生までの児童を対象として国からもらうことができます。以下の金額を受給できます。
- 3歳未満:月額15,000円
- 3歳~小学校修了まで:月額10,000円(第3子以降は30,000円)
- 中学生:月額10,000円
※ 以前は所得制限があり、所得が高い家庭は子ども1人につき、月額5000円となっていました。現在は、2024年度10月より、所得制限は撤廃されています。また、第3子以降は月額30,000円支給されます。
児童扶養手当
児童扶養手当は、シングルマザーなどひとり親の家庭のために地方自治体が支給する手当です。
支給額は、児童の人数や受給者の所得によって異なります。
全部支給と一部支給があります。
令和6年4月以降、全部支給では、児童1人につき月額46,690円(大阪市の場合)が支給されています。
一部支給では所得に応じて月額46,680円〜11,010円が支給されます。
※こちらの手当も児童手当と同様に、2024年10月から制度に変化がありました。
第3子以降の支給金額が引き上げられています。
児童育成手当
東京都の市区町村で実施されている制度。他県にはない制度です。
18歳までの児童を対象に支給されるのが児童育成手当。
18歳になった最初の3月31日まで、その児童を扶養するひとり親家庭に対して月額13,500円が支給されます。
※ 所得制限があり
特別児童扶養手当
心身ともに障害を持っている20歳未満の児童を持つ家庭を対象としています。
障害に該当している児童の福祉増進を目的として、国から支給される制度です。
障害の等級のうち1・2級に該当する児童の親あるいは監護者が手当を受け取る仕組。
所得制限額を超えた場合は支給の対象外となります。支給額は以下のとおりです。
・1級:56,800円
・2級:37,830円
※2025年4月より適用されている金額です。
母子家庭・父子家庭の住宅手当
20歳未満の児童を持つひとり親。
月に10,000円を超える家賃を支払っている世帯主が対象です。
※ 支給条件は全国の自治体によって異なります。
※生活保護の場合
どのような経済状況の世帯であっても健康で文化的な最低限の生活を送れるように。
経済的な保障を目的としています。
生活保護は個人ではなく世帯単位で支給されるため、一人での申請はできません。
生活保護は、保護基準のもとに審査が行なわれます。世帯の状況を考慮したうえで支給されます。
自立支援訓練給付金を利用しましょう!
自立支援教育訓練給付金のことも頭に入れておきましょう。
厚生労働省と各地域の自治体によって実施されている支援事業です。
仕事に有利な資格取得のための講座を修了すると、経費の60%、年間で上限20万円の受給が可能です。
つまり、講座にかかったお金の半分以上がキャッシュバックされる仕組みです。
キャリアアップを見据えて考えてみてはどうでしょうか?
各自治体に問い合わせましょう。
まとめ
シングルになると、仕事、子供の養育費、今後のことをどうしていくか。
いろいろな問題を一人で抱えていかなくてはいけません。
国や自治体が用意している助成金制度や免除・減額制度、自立支援訓練制度等を活用し、
ママさんやパパさんの負担を少しでも減らしていきましょう。
どんなことでも一番優先させるべきことは子どものことです。
悩みをいっしょに考えてくれる制度もあります。
一人で抱え込まず、やっていきましょう。
※掲載内容は2025年4月末時点の情報です。
最新の制度内容は公式サイト等をご確認ください。