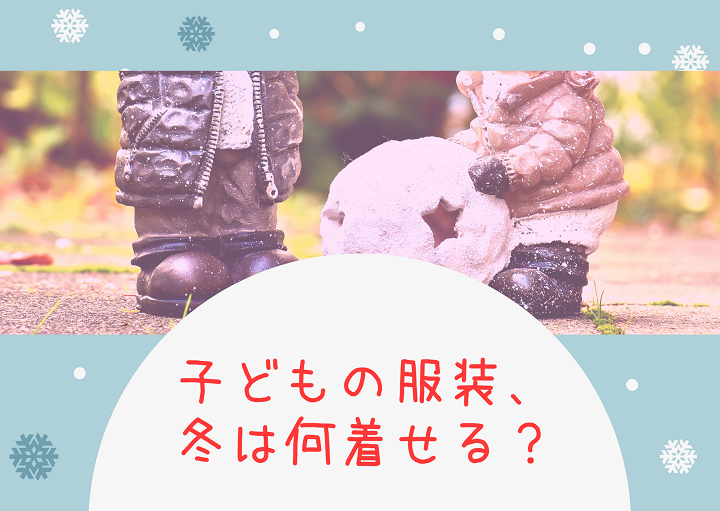2025.10. 3
おもちゃの取り合いに対して親ができること!そもそもなぜ我が子はおもちゃを奪うの?
いつも友だちとおもちゃの取り合いになってしまう・・・そんな時どうすればいいの?
こんにちは!「志木・朝霞のママさんを応援!」ステキライフ編集部です♪
おもちゃを取り合うトラブルには困ってしまいます💦
子ども同士で遊んでくれるのは嬉しいですが...💦
取り合いはだめと教えても、いつの間にかまた奪い合いになっていることも...。
そんな子ども同士のトラブル...どう対処していいのか分からない人も多いのではないでしょうか❓
今回はおもちゃを取り合う子どもの気持ちの解説していきます。
また、トラブル解決の手助けになる情報を紹介します。
なぜおもちゃを取り合うのか子どもの気持ちを知りましょう。
寄り添いながら成長の手助けができるかもしれません。

子どもがおもちゃを奪うのはなぜ?
一般的におもちゃの奪い合いが始まるのは、1歳近くになってからです。
その理由は、成長するにしたがい自我が出てくることにあります。
「自分がおもちゃを使いたい」という、おもちゃへの「執着」が生まれるためです。
子どもの成長過程の一つとしてとらえましょう✨
2~3歳くらいの頃は、子どもはまだ自分の物と他人の物の区別がつけられないことがあります。
そのために目の前にあるおもちゃは、自分のおもちゃだと思いこみ取り合いになってしまうのです。
自分の気持ちを相手の友だちに言葉でどう伝えたらいいのか分かりません。
手が先に出てしまうのも取り合いになる理由の一つです。
保育士はどんな対処をしてるの?
子どものお世話に慣れている保育士は、年齢に合わせた対応をとっていることが多いようです。
● 1歳までの子どもは、特定のおもちゃへの執着があまりありません。
他のおもちゃを渡せばそれで解決する場合もあります。
ただし、思わず手がでしまうこともあるので、ケガにならないよう注意が必要です。
● 1〜3歳までの子どもは、おもちゃの取り合いが多くなります。
どう解決したらいいのかという解決法を知らない時期です。
そのため相手の友だちに、言葉で自分の気持ちを伝える方法を教えるようにします。
「おもちゃを貸して」「ありがとう」「後でね」など。
自分の気持ちを伝える言葉があることを根気よく教えていく時期です。
● 4歳頃になると、友だちの気持ちや自分の行動について考えることができるようになっていきます。
「どうしたら仲良く遊べるかな?」「おもちゃを取られるとどんな気持ちかな?」など。
相手の気持ちや自分の行動を考えるきっかけになる言葉をかけてあげましょう。
どうしたらいいのか一緒に考えてあげると◎!
子どもだけで解決できるように少しずつ導いていきます。
おもちゃの取り合いに対してパパ・ママがきること
子どもの人数よりもおもちゃが少ないと、どうしても取り合いになってしまいます。
そのため楽しく遊べる数のおもちゃを用意する。
おもちゃの数が足りない場合は公園などへ行くことを考えたほうがいいかもしれません。
またおもちゃの取り合いでケガをしてしまうと大変です。
あまり親が介入しすぎないほうが良い場合もあります。
しかし、ケガがないように見守ることは大切な大人の役目です。
手が出そうになった時やケンカになった時、
友だちを叩くのではなく言葉で自分の気持ちを伝えるように教えましょう。
でもいつもおもちゃを貸してあげる必要はありません。
自分の気持ちも大切だということを学ぶ必要があります。
「どうしても嫌だ」という時は、子どもの気持ちを尊重してあげることも大切!
親が「今は自分で使いたいのね?」と子どもの気持ちを代弁してあげましょう。
子どもは親に共感してもらったことで落ち着くことができます。
貸せない時があっても良いと思い、子どもの気持ちに寄り添うことも大事です。
まとめ:子どもの成長につながる対応をしよう
「何度も教えているのに、なぜまた取り合いになるのか」と思いがちです。
子どもは一度で理解できるわけではなく、何度も経験しながら少しずつ学んでいきます。
おもちゃの取り合いになると親は困って疲れてしまいますよね。
子どもはゆっくりと成長していくのを忘れないようにしましょう。
自分の気持ちを大切にしながらも相手の気持ちが理解することができるように教えていきましょう。
子どもの成長につながる対応を親子で学べる機会です。